近畿、九州、中四国と梅雨いりしましたね。沖縄は梅雨が明けたそうです。沖縄では「ハーリーの鐘が鳴ると梅雨があける」と言われていて、糸満のハーリーが5月30日に行われ、6月8日に梅雨が明けました。まさにそうなりましたね。季節って旧暦で回っているんじゃないかと思うくらい、いつも思います。
西表島にいた頃は部落対抗のハーリー大会があり、私も診療所のある租納集落のメンバーとして参加しました。1年目は自分が参加しましたが、2年目は平日だったのでその時、地域医療の実習に来ていた初期研修医の先生に参加してもらいました。彼は残念ながら出られませんでしたが。。。
ハーリー(ハーレーとも言う)を漕ぐのは意外と難しくて、しっかりと足を踏ん張れる場所が船にないんです。船底にうまい具合になんとか踏ん張るところを作って漕ぎます。漕ぐのもタイミングが他のメンバーとズレると如実に遅くなります。
みんなで息を合わせるために大会の数週間前から皆、仕事があるので朝5時くらいから海岸に集まって練習をします。時に長老的な人が差し入れを持ってきてくれたり。あの時、食べた前日に釣ってきたというカツオは身がプリッとしていてすごく美味しかったのを覚えています。
そうやって、皆で力を合わせた記憶というのは絆を深めてくれます。本州でもだんじりやお神輿といった力を合わせる系のお祭りは人気ですよね。地域の青年同士の絆も深まると思います。でも、最近はアルバイトでお神輿の担ぎ手を雇っているところもあるのだとか。ちょっと寂しいような気もしますね。
お祭りは地域の継続にかなり重要な要素だと思っています。
これから夏に向けて どんどん暑くなっていきますね。最近の夏は殺人的な暑さが続いています。
どんどん暑くなっていきますね。最近の夏は殺人的な暑さが続いています。
そう、暑いといえば今回の話題は熱中症です。熱中症には3段階あります。
Ⅰ度(軽症)
症状 失神、立ちくらみ、吐き気、頭痛、筋肉のけいれんなど
Ⅱ度(中等症)
体がぐったりする、力が入らないなど
Ⅲ度(重症)
呼びかけの反応がおかしい、反応しない、42度を超える高体温、けいれんなど
Ⅱ度、Ⅲ度は病院受診が必要です。特にⅢ度は命の危険性が高いので救急車を呼んですぐに冷却する必要があります。ちなみに重症の熱中症の方の処置は大変で、救命救急室のメンバー総出で冷却しないといけないくらいです。全身に霧吹きをしたり、氷嚢で頭、脇や鼠蹊部などを冷やしたり、冷たい点滴を一気に入れたり、鼻から胃へ管を通してお腹の中へ冷水を入れて冷やしたりします。
大抵の場合はⅠ度くらいで済みます。
皆さんの関心のあることはどうすれば防げるか?ですよね?
一番、大切なことは涼しい場所にいるということです。そして、喉が渇いたら水分をとることです。Ⅰ度熱中症の治療も涼しいところで休み、喉が渇いていたら水分補給することです。人間の体はよくできたもので、喉が渇いたら飲むで十分なのです。
経口補水液やスポーツドリンクを売る会社は熱中症予防に喉が渇く前にこまめに水分補給するように、しかも経口補水液やスポーツドリンクを飲みましょうなどと勧めますが、必要ありません。
運動中はスポーツドリンクの摂取は最適ですが、運動もしていないのにスポーツドリンクを飲むのはジュースを飲んでいるのと変わらないです。お茶や水で十分です。
また、寝る前に水分補給をとも言われることがありますが、これも不要です。寝ている間におしっこに行きたくなって、ちゃんと眠れなくなります。それよりも涼しくして、快適な睡眠環境を築くことが大切です。
以上を踏まえ、暑い日は極力、涼しい場所で過ごすようにし、移動が必要ならなるべく日陰を歩きましょう。喉が渇いたな、何か飲みたいなと感じたら水分をとるようにしましょう。
暑い夏を乗り切るために熱中症には気をつけて過ごしましょう。
当法人は訪問看護ステーション「こさか訪問看護ステーション」も運営しております。2024年6月に開設され、約1年が経ちました。まだ、患者さんは少ないですが、開設して良かったと本当に実感しています。
何が良いかというと在宅患者さんの医療的ケアが本当に充実するし、便利なんです。その肝はやはり担当医師との情報共有が速くて、スムース!お互いに顔の見える関係なので伝えたいことを伝えやすいです。
これは訪問看護ステーション単独の事業所であったり、病院付属の訪問看護ステーションにはない強みだと思います。
病院付属の訪問看護ステーションを利用している患者さんの主治医は近隣の開業医か同じ病院の医師です。開業医だとあまり親しくなかったり、連絡が取りづらかったりします。連絡手段がFAXか電話のみしかないことも。病院の医師は異動があったり、他院に仕事に行っていることもあります。
でも、当院なら院内のSNSですぐに情報共有できたり、主治医にすぐに相談できます。院内SNSのまた良いところは主治医だけでなく、他の医師も閲覧できるので、異なる視点でアドバイスが得られることもあるので、より漏れのない質の高い診療となります。
また、他院の患者さんでもちょっとしたことなどは当院医師に意見を聞くことも簡単にできてしまいます。
しかも、訪問診療にも訪問看護師が同行することもあるので、その患者さんについては診察についてくる看護師がそのまま訪問看護に来てみてもらえますし、診察の内容を訪問看護ステーション内ですぐに情報共有できます。もちろん、医師の記載したカルテを見ることもできます。
訪問看護ステーション併設のクリニックとしては「情報共有」が肝心です。より的確な情報共有、質の良い相談をできるよう、先日、SBARという医療安全と患者さんの医療の質向上のためのツールを使う練習会をしました。
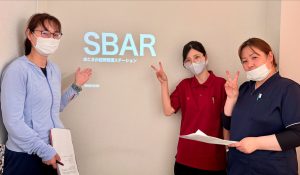 SBARはチームSTEPPSのツールの一つです。チームSTEPPSについてはこちらをご参照ください。(https://doctor.mynavi.jp/column/teamstepps/)
SBARはチームSTEPPSのツールの一つです。チームSTEPPSについてはこちらをご参照ください。(https://doctor.mynavi.jp/column/teamstepps/)
SBARとは
Situation (状況)
Back ground (背景)
Assessment (アセスメント、診断)
Recommendation(おすすめ)
の順に問題を伝達する方法です。
例えばこのようにプレゼンテーションします。
「〇〇さん85歳男性。今朝から呼吸苦があり、SpO2 85%に下がっています。慢性心不全と慢性心房細動があり、フロセミド40mg(利尿剤)を毎日内服しています。心不全が悪化していると思います。酸素投与開始とフロセミドの増量をするのはいかがでしょうか?」
となります。まずSituation(状況)は85歳男性が呼吸苦があり、SpO2が85%に低下していること。次にBack ground(背景)は慢性心不全と慢性心房細動でフロセミドという利尿剤を飲んでいること。Assessment(診断)は心不全の悪化。Recommendation(おすすめ)は酸素投与の開始とフロセミドの増量です。
このように決まった形式で系統だって伝えることで、状況をイメージしやすく、的確な判断もしやすくなります。
このような勉強会も定期的に開催するつもりなので、こさか訪問看護ステーションの看護レベルはどんどん上がっていくものと考えています。
もし、ご家族の方で訪問看護が必要そうだなと思われる方がいらっしゃいましたら、ぜひご指名いただけると幸いです。
訪問看護のお問い合わせは
こさか訪問看護ステーション
TEL 080-2591-4332 または 078−597−8339