当法人は訪問看護ステーション「こさか訪問看護ステーション」も運営しております。2024年6月に開設され、約1年が経ちました。まだ、患者さんは少ないですが、開設して良かったと本当に実感しています。
何が良いかというと在宅患者さんの医療的ケアが本当に充実するし、便利なんです。その肝はやはり担当医師との情報共有が速くて、スムース!お互いに顔の見える関係なので伝えたいことを伝えやすいです。
これは訪問看護ステーション単独の事業所であったり、病院付属の訪問看護ステーションにはない強みだと思います。
病院付属の訪問看護ステーションを利用している患者さんの主治医は近隣の開業医か同じ病院の医師です。開業医だとあまり親しくなかったり、連絡が取りづらかったりします。連絡手段がFAXか電話のみしかないことも。病院の医師は異動があったり、他院に仕事に行っていることもあります。
でも、当院なら院内のSNSですぐに情報共有できたり、主治医にすぐに相談できます。院内SNSのまた良いところは主治医だけでなく、他の医師も閲覧できるので、異なる視点でアドバイスが得られることもあるので、より漏れのない質の高い診療となります。
また、他院の患者さんでもちょっとしたことなどは当院医師に意見を聞くことも簡単にできてしまいます。
しかも、訪問診療にも訪問看護師が同行することもあるので、その患者さんについては診察についてくる看護師がそのまま訪問看護に来てみてもらえますし、診察の内容を訪問看護ステーション内ですぐに情報共有できます。もちろん、医師の記載したカルテを見ることもできます。
訪問看護ステーション併設のクリニックとしては「情報共有」が肝心です。より的確な情報共有、質の良い相談をできるよう、先日、SBARという医療安全と患者さんの医療の質向上のためのツールを使う練習会をしました。
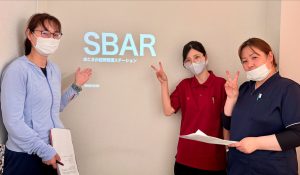 SBARはチームSTEPPSのツールの一つです。チームSTEPPSについてはこちらをご参照ください。(https://doctor.mynavi.jp/column/teamstepps/)
SBARはチームSTEPPSのツールの一つです。チームSTEPPSについてはこちらをご参照ください。(https://doctor.mynavi.jp/column/teamstepps/)
SBARとは
Situation (状況)
Back ground (背景)
Assessment (アセスメント、診断)
Recommendation(おすすめ)
の順に問題を伝達する方法です。
例えばこのようにプレゼンテーションします。
「〇〇さん85歳男性。今朝から呼吸苦があり、SpO2 85%に下がっています。慢性心不全と慢性心房細動があり、フロセミド40mg(利尿剤)を毎日内服しています。心不全が悪化していると思います。酸素投与開始とフロセミドの増量をするのはいかがでしょうか?」
となります。まずSituation(状況)は85歳男性が呼吸苦があり、SpO2が85%に低下していること。次にBack ground(背景)は慢性心不全と慢性心房細動でフロセミドという利尿剤を飲んでいること。Assessment(診断)は心不全の悪化。Recommendation(おすすめ)は酸素投与の開始とフロセミドの増量です。
このように決まった形式で系統だって伝えることで、状況をイメージしやすく、的確な判断もしやすくなります。
このような勉強会も定期的に開催するつもりなので、こさか訪問看護ステーションの看護レベルはどんどん上がっていくものと考えています。
もし、ご家族の方で訪問看護が必要そうだなと思われる方がいらっしゃいましたら、ぜひご指名いただけると幸いです。
訪問看護のお問い合わせは
こさか訪問看護ステーション
TEL 080-2591-4332 または 078−597−8339